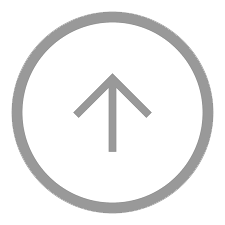パンの摂取方法
食パンは小麦アレルギ―の心配がない場合は、初期食から食べられます。はじめはミルクなどに浸してパン粥として与えて。
バターロールやフランスパンは脂質や塩分が多いため離乳食期には不向きです。1歳以降から少量ずつ与えましょう。また調理パンや菓子パンは添加物も多いため、原材料を確認して良質の物を選びましょう。
※食物アレルギーが疑われる症状がみられた場合、自己判断で対応せずに、必ず医師の診断に基づいて進めましょう。
うどん・そうめんの摂取方法
小麦アレルギーの心配がない場合は、初期食から食べられます。くたくたになるまで茹で、短く切ってあげましょう。乾麺は塩分が多いため、必ず下茹でをしましょう。
※食物アレルギーが疑われる症状がみられた場合、自己判断で対応せずに、必ず医師の診断に基づいて進めましょう。
スパゲッティ・マカロニの摂取方法
うどんやそうめんよりも硬く、噛み切りにくい食材です。柔らかく茹で、短く切ってあげれば中期食以降から食べられます。小麦アレルギーの心配があるため、はじめは少量から与えてください。
※食物アレルギーが疑われる症状がみられた場合、自己判断で対応せずに、必ず医師の診断に基づいて進めましょう。
中華めん・焼きそばの摂取方法
原材料に卵が使われている場合があるため、卵アレルギーの心配がある方は注意が必要です。心配のない場合は、茹で時間を長めにし、短く切ってあげて1歳以降から与えましょう。
焼きそばめんは、表面に油が添加されています。具材やスープにも塩分や脂質が多くなりやすいため、幼児食以降も食べ過ぎには注意をしましょう。
※食物アレルギーが疑われる症状がみられた場合、自己判断で対応せずに、必ず医師の診断に基づいて進めましょう。
そばの摂取方法
アレルギーの心配があるため、満1歳になるまでは与えないようにしましょう。1歳以降は様子を見ながら少量ずつ与えます。
※食物アレルギーが疑われる症状がみられた場合、自己判断で対応せずに、必ず医師の診断に基づいて進めてください。
ホットケーキ粉の摂取方法
小麦粉や牛乳、卵などで手作りしたものは、アレルギーの心配がなければ後期食から食べられます。ただし市販のものは添加物を含むため注意が必要です。赤ちゃん用などを使用し、毎日使うようなことは避けましょう。
※食物アレルギーが疑われる症状がみられた場合、自己判断で対応せずに、必ず医師の診断に基づいて進めましょう。
山芋の摂取方法
生のまま食べると、手や口のまわりが赤くかゆみが出る可能性もあります。中期食以降から食べられますが、必ず加熱をして与えましょう。
※食物アレルギーが疑われる症状がみられた場合、自己判断で対応せずに、必ず医師の診断に基づいて進めましょう。
ごまの摂取方法
いりごまは消化が悪く、気管に入るなどの危険がるため注意が必要です。すりごまにして和え衣として使用しましょう。
アレルギーの心配もあるため、後期食以降に様子を見ながら少量ずつ与えましょう。練りごまも同様に後期食以降に。ごまは油分が多いので与え過ぎないようにしましょう。
※食物アレルギーが疑われる症状がみられた場合、自己判断で対応せずに、必ず医師の診断に基づいて進めましょう。
ピーナッツ(ナッツ類)の摂取方法
粒のまま食べられるようになるのは、幼児期以降です。それまでは誤飲の危険もあるため手の届かない場所に保管しましょう。
ペースト状のものも脂質が多くアレルギーの心配があります。無糖を選び、後期食以降に様子を見ながら少量ずつ与えましょう。
※食物アレルギーが疑われる症状がみられた場合、自己判断で対応せずに、必ず医師の診断に基づいて進めましょう。
たらの摂取方法
低脂肪で初期食から食べられる白身魚ですが、たらは例外です。アレルギーの心配があるので後期食以降から少量ずつ与えてください。塩の添加のない生たらを選び、皮は取りましょう。
※食物アレルギーが疑われる症状がみられた場合、自己判断で対応せずに、必ず医師の診断に基づいて進めましょう。
青魚(あじ・いわし・さんま)の摂取方法
青魚は脂質が多くアレルギーの心配があるので、後期食後半から新鮮なものを十分に加熱して少量ずつ与えてください。小骨はのどに刺さる危険があるため、取り除いてあげましょう。
※食物アレルギーが疑われる症状がみられた場合、自己判断で対応せずに、必ず医師の診断に基づいて進めましょう。
エビ・カニ・イカ・タコの摂取方法
えびやかにはアレルギーの心配があるため、完了期食以降に新鮮なものを十分に加熱をしてから少量ずつ与えてください。えびにアレルギーのある場合はサクラエビにも注意しましょう。
イカやタコは弾力があり食べにくい食材です。細かく刻んであげるか、奥歯が生えて、しっかり噛めるようになってからにしましょう。
※食物アレルギーが疑われる症状がみられた場合、自己判断で対応せずに、必ず医師の診断に基づいて進めましょう。
たまごの摂取方法
よく加熱した卵黄を初期食後半以降から様子を見ながらはじめます。まずは固ゆでにしたゆで卵を作り、ペースト状にした黄身をほんの少しから試します。
慣れてきたら量を増やし、全卵は中期食以降にしましょう。卵は食中毒の可能性もあるため、乳児期では必ずよく加熱をしてください。
※食物アレルギーが疑われる症状がみられた場合、自己判断で対応せずに、必ず医師の診断に基づいて進めましょう。
牛乳・ヨーグルトの摂取方法
牛乳は飲み物としては1歳以降からにしましょう。ミルク煮などの調理に使用する場合は後期食以降から使用できます。アレルギーの心配があるためはじめはごく少量にしてください。
ヨーグルトは無糖を選べば中期食以降から食べられます。牛乳と同じくアレルギーの心配があるため、少量ずつから与えてください。
※食物アレルギーが疑われる症状がみられた場合、自己判断で対応せずに、必ず医師の診断に基づいて進めましょう。
塩分、脂肪分、油分
◇厚揚げ・がんもどきの摂取方法
脂質が多いため離乳食期には不向きです。食べさせる場合は内側の豆腐部分のみを与えてください。大豆アレルギーの場合は注意しましょう。
◇油揚げの摂取方法
油抜きをしても脂質が多すぎます。1歳以降に、細かく刻んで少量なら与えても良いでしょう。大豆アレルギーの場合は注意しましょう。
◇ドライフルーツ(レーズン・プルーン)の摂取方法
栄養価は高いですが糖分も高いため与え過ぎには注意しましょう。塩や油分が添加されていないものを選び、湯で洗い柔らかくもどしてから少量のみ与えてください。
◇赤魚(まぐろ・かつお)の摂取方法
白身魚よりも脂質が多いため、中期食以降から少量ずつ与えてください。まぐろは赤身やツナ缶を、かつおは背身を選びましょう。ツナ缶は食塩無添加のノンオイルのものを選びましょう。
◇かまぼこ・ちくわ・はんぺんの摂取方法
添加物や塩分、脂肪分が多く含まれるため、離乳食期には控えるのが良いでしょう。製品によって原材料が異なるため、表示をよく確認して添加物の少ない良質なものを選んでください。はんぺんはつなぎに卵白が使われているので、卵アレルギーの場合には注意が必要です。
◇肉類の摂取方法
鶏ささみや鶏むね肉は脂質が少ないため中期食から食べられます。十分に加熱してよくほぐして与えましょう。鶏もも肉は脂質が多いため皮を取り、後期食以降から与えてください。 牛肉や豚肉は赤身を選び、後期食後半からにしましょう。
ひき肉は傷みが早いため、新鮮なものを選び早めに使い切りましょう。特に合いびき肉は脂質が多いため一度茹でこぼして油抜きをするのが良いでしょう。
◇ハム・ソーセージの摂取方法
添加物や塩分、脂肪分が多く含まれるため、離乳食期には出来る限り控えましょう。製品によって原材料が異なるため、表示をよく確認して添加物の少ない良質なものを選んでください。
◇生クリームの摂取方法
生クリームは牛乳の脂肪分のため脂質が多く含まれています。そのため離乳食期では控え、1歳以降も食べ過ぎには注意しましょう。植物性油脂使用クリームやコーヒークリームは添加物を含みます。幼児期以降も避けるのが良いでしょう。
◇チーズの摂取方法
プロセスチーズ、カマンベールチーズは塩分・脂肪分が多いので、離乳食期ではごく少量にしましょう。クリームチーズも脂質が多く高エネルギーのため食べ過ぎには注意が必要です。カッテージチーズは離乳食向き、裏ごしタイプを使用しましょう。
◇油・バターの摂取方法
バターは消化吸収がよく、少量なら後期食以降に風味づけとして使用できます。無塩タイプを使用しましょう。マーガリンは安全性が問題視されているトランス脂肪酸が含まれるため使用は控えましょう。サラダ油はバターなどの乳脂肪に慣れてから、炒め油などでごく少量から与えます。
◇調味料の摂取方法
塩・味噌・醤油などの調味料は後期食以降から風味づけ程度にごく少量から与えます。みりんや酒は離乳食期にはあえて使う必要はありませんが、後期食以降に少量かつ加熱して与える場合は問題ありません。
ト マトケチャップは味が濃いので離乳食期にはトマトピューレがおすすめです。マヨネーズは生卵が含まれているため1歳未満の子には必ず加熱が必要です。その他の調味料も乳児期は大人の1/4~1/3、幼児期も1/2程度を目安に薄味を心がけましょう。
◇香辛料(カレー粉・こしょう)の摂取方法
刺激が強いため、基本的に離乳食期では使用しないのが良いでしょう。カレー粉は1歳以降から風味づけ程度に使えます。
消化について
◇野菜類の摂取方法
皮や種は消化が悪く内臓に負担がかかるため離乳食期には取り除いてあげましょう。繊維の少ない野菜から柔らかく煮て、葉物はよく茹でてから繊維を断ち切るようにみじん切りにしてあたえてください。
◇きのこ類の摂取方法
噛み切りにくいため、後期食以降から細かく刻んであげましょう。とろみをつけてあげると食べやすくなります。
◇貝類(ほたて貝柱・あさり・しじみ)の摂取方法
ほたて貝柱は十分に加熱しほぐせば、少量なら中期食から食べられます。あさりやしじみはだし汁のみなら中期食から食べられますが、身は加熱をすると硬くなるため後期食以降に刻んであげましょう。
窒息について
ナッツや豆類、ミニトマトなど小さくて丸い形状のものは窒息の恐れがありますので十分ご注意ください。また、もち、寒天、のりなど噛みきりづらいものも避けてください。
◇もちの摂取方法
のどに詰まらせやすいため、歯が生え揃い、よく噛めるようになった2~3歳以降から与えましょう。細かく切り、食事中はお子さまから目を離さないようにしてください。
◇こんにゃくの摂取方法
噛み切りにくく、のどに詰まらせる心配があるため注意が必要です。離乳食期では使用を避けましょう。乳児期以降も小さく切り食べやすくしてあげましょう。
◇水煮大豆の摂取方法
そのまま食べさせるとのどに詰まらせてしまうことも。離乳食期には消化の悪い薄皮を必ず剥き、刻んだり潰したりして与えましょう。
はちみつの注意点
◇はちみつがダメな理由とは
使いやすく、自然そのままの食品で甘味も優しいので安心安全と思われがちな「はちみつ」ですが、1歳未満の赤ちゃんに与えるのは実はNG!その理由は、「ボツリヌス菌」という食中毒を起こす菌が含まれている可能性があるためです。
ボツリヌス菌は熱に強いため、そのまま食べるのはもちろん、加熱して食べることも1歳未満の赤ちゃんには危険です。
自宅では使用しなければ安心ですが、外食時や市販の食品には原材料としてはちみつが含まれていることもあるため、1歳未満の場合はできるだけチェックしてあげましょう。
◇もし食べてしまったら?
もし、ボツリヌス菌を含んでいるはちみつを食べてしまったら・・・乳児ボツリヌス症という感染症になってしまう可能性があります。稀な感染症ではありますが、消化器官が未熟で、腸内細菌の環境が整っていない1歳未満の赤ちゃんには危険です。
1歳以上になると腸内環境が整ってきて体内で菌が繁殖する可能性が低くなるため食べても大丈夫だと言われています。
乳児ボツリヌス症は1歳未満の赤ちゃんが罹ってしまうと便秘になる、元気がなくなる、おっぱいやミルクの飲みが悪くなるなどの症状が出てきます。気付かずに食べてしまっていたということもあるため、このような症状があったり、様子が気になる時は病院で診てもらいましょう。
◇黒砂糖の摂取方法
はちみつ同様、ボツリヌス菌が混入している恐れがあります。内臓の機能が未熟な1歳未満の子には与えないようにしましょう。
◇刺身・生肉の摂取方法
生ものは食中毒の恐れがあるため、内臓機能が未熟な乳児期には与えません。幼児期以降も新鮮なものを選んであげましょう。