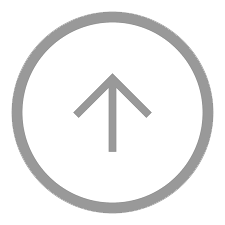生野菜全般
赤痢菌、病原性大腸菌、カンピロバクター
カンピロバクターの潜伏期間は1~7日で症状としては悪心、嘔吐、下痢、腹痛などの消化器系に現れるほか、発熱を伴うこともあります。抵抗力の弱い方では重症化することもあります。※1
生野菜は鮮度の良いものを使用し、まな板や包丁、手指の洗浄など衛生面にも気をつけましょう。
赤痢菌は1~7日間の潜伏期間を経て、大腸炎、激しい下痢や腹痛、嘔吐や発熱が合わられます。乳幼児では重症化しやすく死亡率も高くなります。毒素を不活化させるためには、80℃で10分以上加熱する必要があります。※2、※3
また、食材を扱ったまな板や手指、調理器具からの二次感染・経口感染予防のため、洗浄や消毒は徹底しましょう。
病原性大腸菌は体内に入り4~8日の潜伏期間を経て腹痛や下痢、発熱などを伴います。悪化すると血便やその他合併症を併発することもあります。※4
※1参照:厚生労働省 カンピロバクター食中毒予防について(Q A)
※2参照:kao 細菌性食中毒 感染型
※3参照:東京都福祉保健局 食品衛生の窓
※4参照:東京都福祉保健局 食品衛生の窓
せり(毒ぜり)
自然毒
毒ぜりは全草に猛毒のポリイン化合物が含まれています。嘔吐、下痢、腹痛以外にもめまいや動悸、痙攣、意識障害、呼吸困難など重篤な症状に至る場合もあります。
※せりの旬である春には草丈も短いいために間違え、根茎はわさびと間違えることも多いため、注意が必要です。葉は見た目が似ていても香りが違うために判断材料となります。
参照:厚生労働省 自然毒のリスクプロファイル:高等植物:ドクゼリ
ジャガイモ
ソラニン、チャコニン
じゃがいもの芽や緑色になった部分に多く含まれるのがソラニンやチャコニンという天然毒です。吐き気、腹痛、嘔吐、下痢、めまいなどの症状が出ます。
じゃがいもはあまり光が当たらない涼しい場所で保管し、芽が出たり皮が緑色に変色した場合はその部分を取り除いて調理をしましょう。
参照:農林水産省 ジャガイモによる食中毒を予防するために
きのこ
自然毒、ヒスタミン、リステリア菌
毒をもつきのこは数多くありますが、口にして10分~24時間後に嘔吐、腹痛、下痢などを起こします。その他にも痙攣や幻覚を起こすもの、脳にダメージを与えるもの、死亡に至るものもあります。キノコ狩りなどで自己判断による喫食は絶対に避けましょう。※1
きのこは新鮮なものを、よく火を通してから、食べるようにしましょう。 生や加熱が不十分な状態で食べると、アレルギー症状や食中毒が起こることがあります。※2
また松茸については採取して日が経つと傷み、ヒスタミンという食中毒を起こす物質が発生し、吐き気やおう吐が起きることがあります。※3ただし、マッシュルームは新鮮なものであれば生食ができます。※4
保存状態にもよりますが収穫から冷蔵保存で3日~4日以内は生で食べられると言われていますが、少し黒くなってしまったものは十分に火を通して食べるようにしましょう。※5
※1参照:東京都福祉保健局 食品衛生の窓 キノコ食中毒
※2参照:食品安全委員会 食品安全関係情報詳細
※3参照:J-STAGE 栄養と食糧
※4参照:JAグループ マッシュルーム
※5参照:ミツクラ農林 マッシュルームの豆知識
白インゲン豆
レクチン
たんぱく質の一種で、摂取して1~3時間程度で吐き気や腹痛、下痢などの消化器系に症状が出ます。レクチンによる食中毒は生の状態や加熱不足の状態で起こります。
そのため、乾燥の豆は十分に浸水して柔らかくなるまでしっかりと加熱する(ゆでる)という工程を確実に行うことで防ぐことが出来ます。
参照:厚生労働省 報道発表資料 白インゲン豆の摂取による健康被害事例について
びわの種子
シアン化合物
びわの種子をはじめ、アンズやウメ、モモ、スモモ、サクランボなどのバラ科植物の種子や未熟な果実には、天然の有害物質(シアン化合物)が含まれています。
シアン化合物を一度に大量にとると、頭痛やめまい、悪心、嘔吐などの中毒症状を起こす可能性があり、海外では健康被害や死亡例が報告されています。
びわの種子を使った料理や種子を粉末にした加工品を食べる場合は十分に注意をし、果実は熟した状態で食べるようにしましょう。